
店内の朝、焙煎機の前で最初の熱が入ると、
豆の色と香りが少しずつ表情を変えていきます。
先日開催した少人数制の「珈琲焙煎ワークショップ」では、
その変化を行程ごとに確かめながら、焙煎度と味の関係を体験しました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
開催概要
テーマ
焙煎の基礎とテイスティング(浅煎り〜中深煎り〜深煎り)
構 成
基礎レクチャー → 焙煎デモ → 焙煎違いの飲み比べ → 質疑応答
定 員
少人数制(対話しながら進める形式)

当日の流れ
- 生豆の見方とプロファイル設計(火力と時間の組み立て)
- ハゼ(1st/2nd)の聞き取りと進行管理
- 焙煎違いテイスティング(浅・中深・深)
- 抽出との関係(挽き目・温度・比率のヒント)
小さな学び(参加者のメモより)

浅煎り=酸っぱい、深煎り=苦い、では終わらない。温度や抽出で印象が整う。
参加者メモ
冷めるにつれ甘みが前に出る。時間の経過も味わいの一部。
参加者メモ
家で試すときのヒント
- 記録する:挽き目・湯温・抽出時間・感想を短くメモ。次回の基準が作れます。
- 一度に変えるのは一項目:比率 → 時間 → 温度の順で調整すると違いが分かりやすい。
- 温度の使い分け:甘みを出すならやや低め、キレを出すならやや高め。

当日の空気
焙煎の音に耳を澄ませ、湯気の向こうで豆の表情が変わるのを待つ時間。
合間の小さな会話から、それぞれの暮らしに寄り添う一杯の形が見えてきました。

この日の記録。ご参加ありがとうございました。
まとめ
焙煎は、香り・音・色を重ねて捉える体験でした。
今回の学びが、日々の一杯を少しだけ心地よくしてくれたら嬉しいです。
次回の開催が決まりましたら、店頭とサイトでお知らせします。
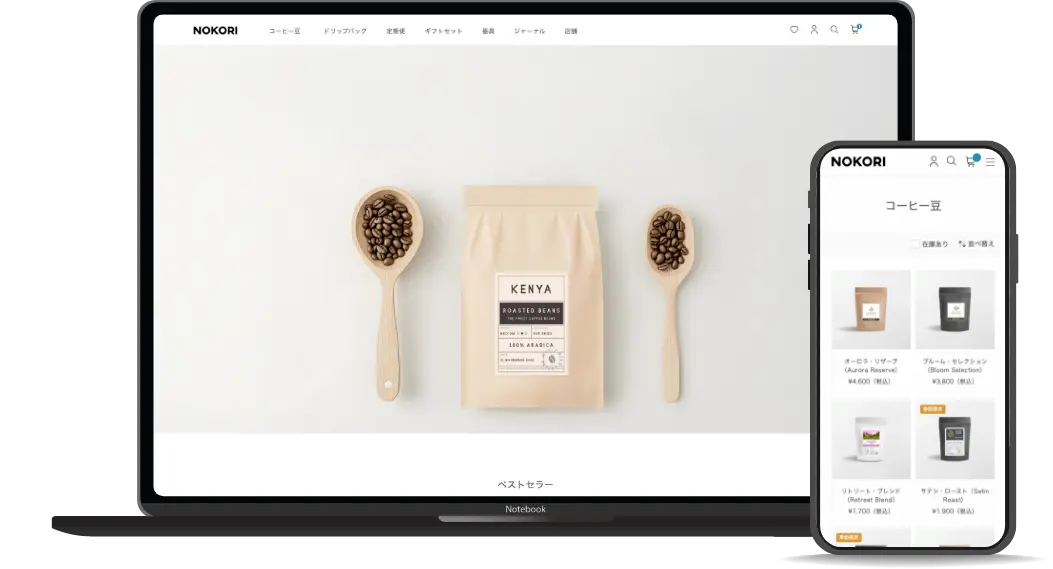
コメントは受け付けていません。